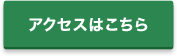(前回の続き)単純問題グループでない問題(高校受験・数学)
- 2025年10月20日
-
- カテゴリ:
- 全学年対象すべて
こんにちは。
大塚ゼミナールです。
さて、前回の続きのお話を。
単純問題グループでない問題の話をしましょう。
さて、前回の続きのお話を。
単純問題グループでない問題の話をしましょう。
具体例で、関数にまつわる問題について考えてみましょう。
たとえば、関数の問題が出題される場合の主なバリエーションとして
❶:グラフの式が明示されていて、座標を求める問題
➋:座標や条件を読み解いて、グラフの式を求める問題
❸:グラフのいくつかの座標やX軸・Y軸に囲まれた面積を求める問題
❹:❸に加えて等積変形をする問題
❺:回転体として体積を求める問題
❻:相似や円と組み合わせた融合問題(高難易度)
❼:正方形へ平行四辺形などの条件と組み合わせて座標を求める問題(高難易度)
などが王道といえます。
❶:グラフの式が明示されていて、座標を求める問題
➋:座標や条件を読み解いて、グラフの式を求める問題
❸:グラフのいくつかの座標やX軸・Y軸に囲まれた面積を求める問題
❹:❸に加えて等積変形をする問題
❺:回転体として体積を求める問題
❻:相似や円と組み合わせた融合問題(高難易度)
❼:正方形へ平行四辺形などの条件と組み合わせて座標を求める問題(高難易度)
などが王道といえます。
そのため、問題文や与えられた図式を見て、どのように使う知識を決めてアプローチするかを判断することが要求されます。
ですから、問題文のこの説明がでてきたら…とかこのような位置関係になっていたら…とかの手がかりを探す練習がカギといえます。
各バリエーションの思考練習に適した問題選定を行い、着眼点と解法の伝達が、塾の授業の真骨頂といえるでしょう。
よって、このような単元の学習法としては、まず授業で解いた問題を何も見ない状態で解けるように自学で復習することが第一で必要なことといえます。そのうえで、類題を解き、しっかりと自分の手を動かして納得することが大事です。
ですから、問題文のこの説明がでてきたら…とかこのような位置関係になっていたら…とかの手がかりを探す練習がカギといえます。
各バリエーションの思考練習に適した問題選定を行い、着眼点と解法の伝達が、塾の授業の真骨頂といえるでしょう。
よって、このような単元の学習法としては、まず授業で解いた問題を何も見ない状態で解けるように自学で復習することが第一で必要なことといえます。そのうえで、類題を解き、しっかりと自分の手を動かして納得することが大事です。
前回、お話したこととつながりますが、しっかり仕分けをして単元ごとに戦略を見定めることが成績アップのカギといえます。
しっかりと取り組み、受験合格を目指しましょう。